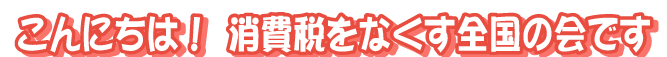保護費減額は違法(「赤旗})、生活保護費の減額 違法状態の放置許されぬ(「毎日」)、高関税と80兆円投資 日本は米の財布ではない(「毎日」)
2025年9月13日
【赤旗】9月10日<主張>保護費減額は違法―国は最高裁判決に従い謝罪を
国・厚生労働省による2013年からの生活保護基準大幅引き下げは違法だと、最高裁判所が下した原告勝訴、国敗訴の画期的な判決(6月27日)から2カ月。福岡資麿厚労相は謝罪すらしていません。敗訴当事者・厚生労働省は、勝訴当事者が反対したにもかかわらず「最高裁判決への対応に関する専門委員会」を省内に強行設置しました。厚労省が選んだ専門委員が最高裁判決の内容を精査して対応を決めるという不誠実極まる異常な姿勢に出ています。
引き下げは違法と訴えた原告と「いのちのとりで裁判全国アクション」などは最高裁判決当日、福岡厚労相にたいし、早期全面解決として真摯(しんし)な謝罪と13年改定前基準との差額保護費の遡及(そきゅう)支給などを求めました。専門委員会設置は、12年間にわたる全国31の訴訟を無いものとし、国民の権利と自由を保障する三権分立を揺るがすような前代未聞なことです。しかも、「専門委員会の結論時期は未定」(同省社会・援護局保護課企画法令係長)という無責任なものです。
■第三者の検討委を
「国民生活の保障及び向上」等を図ることを任務とする(厚生労働省設置法3条)厚労省がすべきことは、最高裁判決を真摯に受け止め、勝利した原告・弁護団と協議し、差額保護費の遡及支給など被害回復をただちに行うことです。「専門委員会」というなら、安倍政権下で自民党の選挙公約を忖度(そんたく)するように基準を引き下げた経緯と再発防止策を提言する第三者の検討委員会こそが必要です。
田村智子委員長をはじめ日本共産党国会議員団は8月19日、最高裁判決を踏まえ厚労省はただちに生活保護利用者に謝罪し、引き下げ分を補償するなど早期全面解決を求める石破茂首相と福岡厚労相への要請書を提出しました。27日には、「いのちのとりで裁判」の原告・弁護団と懇談し、被害回復にむけて意見交換しました。
■国の最低限度保障
憲法25条に基づき、国民の生存権を守る“最後の砦(とりで)”が生活保護制度です。生活保護利用者は基準が大幅に引き下げられたことで、生活扶助費が平均6・5%減額され、その影響が長期間続いた上に、現在の物価高騰、猛暑等で生活はいっそう困難になり、生存権が侵害され続けています。原告の2割を超える232人が亡くなっています。最高裁判決後にも、猛暑なのにエアコンを設置できない神奈川の原告が亡くなりました。
また、生活保護の基準額は、「ナショナルミニマム(国の最低限度保障)」を具体化したものとされており、保護を利用する人だけでなく、最低賃金の額、就学援助費の支給基準、地方税の非課税限度額など50近い制度とも連動・関連して多くの人たちの生活に影響を与えています。
裁判を支えてきた全国生活と健康を守る会連合会(全生連)は「国は生活保護減額違法の判決に従え」を合言葉に、請願署名運動と自治体・議員要請行動を始めています。ナショナルミニマム向上の課題としても、国民的な運動を広げるときです。
【毎日新聞】9月12日〈社説〉生活保護費の減額 違法状態の放置許されぬ
最高裁が違法と断じた状態を放置してはならない。国は直ちに是正に乗り出すべきだ。
2013~15年に生活保護費が最大10%引き下げられた措置に対し、最高裁は6月、減額を取り消す国側敗訴の判決を言い渡した。
減額幅は厚生労働省がデフレなどを理由に、前例のない手法で算定した。専門家にも諮らず決めたことが、裁量権の逸脱・乱用に当たると認定された。
違法とされた以上、国側は原告に謝罪し、影響を受けた受給者全員に本来の額をさかのぼって支払うのが筋だ。
だが、国にそうした姿勢は見えない。
今後の対応を検討するためとして、新たに専門家会議を設置した。厚労省は引き下げ自体が違法とされたのではなく、専門家に諮らなかった手続きに問題があったとの見解を示した。
減額幅をさらに大きくする余地もあったとするデータまで、新たに持ち出した。改めて専門家が引き下げの妥当性を認めれば、補償は必要ないと言わんばかりの態度だ。被害を受けた受給者に真摯(しんし)に向き合う姿勢がうかがえない。
11年間にわたった裁判の末に国は敗訴した。会議で話し合うべきなのは、減額を決めた当時の議論のやり直しではなく、被害回復の具体策であるはずだ。原告側が「最高裁判決が骨抜きにされてしまう」と憤るのは当然だろう。
保護費が減らされた受給者は200万人以上おり、総額は最大3000億円と見込まれる。補償する場合、実務を担う自治体の作業は膨大になる。国は手順などを早急に定める必要がある。
生活保護の金額は、最低賃金や就学援助、医療・介護の保険料減免など40以上の施策を運用する際の基準になっている。それだけ影響は大きい。
減額の措置には、12年衆院選で引き下げを公約に掲げた自民党の意向が強く働いたとされる。生活保護行政をゆがめた反省を踏まえ、政治主導で解決を図るべきだ。
憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための命綱である。全国で1000人を超えた原告は高齢者が多く、既に2割以上が亡くなっている。被害回復の先送りは許されない。
【毎日新聞】9月13日〈社説〉高関税と80兆円投資 日本は米の財布ではない
日本が米国に都合のいい財布として利用されるのではないか。そんな懸念すら抱かせる不平等な取り決めである。
トランプ米大統領が、高関税政策を巡り、日米両政府の合意を実行する大統領令に署名した。日本車に課されていた27・5%の税率は15%になる。
7月に合意してから1カ月以上も経過している。国同士の約束を放置してきた態度は不誠実極まりない。
しかも米国に一方的に有利な内容であることに変わりはない。
関税が下がるとはいえ、トランプ政権前に比べると異例の高さだ。日本車の税率は6倍である。
米政府は関税を主要な収入源とみなしている。自らの利益さえ確保すれば、他国に打撃を与えても構わないと考えているのだろう。
関税軽減の見返りとして、日本は農産物を大量に輸入するなど米側の要求を相次いで受け入れた。
なかでも見過ごせないのは、80兆円規模に上る巨額の対米投資の使途が、米国主導で決められる仕組みとなったことだ。
日米が策定した文書によると、米側だけで構成する委員会が投資先を推薦し、トランプ氏が最終的に選ぶ。日本は委員会に助言する組織にしか加われない。投資を拒めば、米国は再び関税を引き上げられるとも明記された。
トランプ氏は「我々が好きなように使える資金」と発言してきた。米国第一の柱に掲げる「製造業の復活」に投じ、高関税の成果として誇示する狙いとみられる。
しかし、衰退した造船業などへの投資に対しては採算性を疑問視する声が根強い。トランプ氏が意欲を示すアラスカでの天然ガス開発も「巨額のコストがかかり、リスクが大きい」との見方が多い。
日本が活用を予定する政府系金融機関の投融資は公的資金が元手である。トランプ政権からの無理な要求をのまされるばかりでは、国益が損なわれる。
大国が高関税で脅す手法が常態化すれば、世界経済の混乱が深まる。日本は各国と連携し、撤回を粘り強く求めていく必要がある。
対米輸出の減少は日本経済に悪影響をもたらす。雇用などにしわ寄せが及ばないよう、政府は対策に万全を期すべきだ。