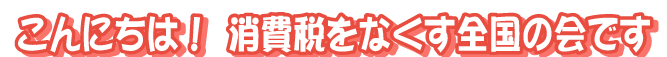株価至上の弊害―労働者守る政治の責任果たせ(「赤旗」)、無責任な歳出拡大危ぶむ(「毎日」)、経済財政の会議 偏った追認を危ぶむ(「朝日」)
2025年11月16日
【しんぶん赤旗】11月15日<主張>株価至上の弊害―労働者守る政治の責任果たせ
株主の利益を最大化することだけを至上命令とする大企業の行動原理が、長期的な経済発展や国民生活の向上を大きく損なっています。
日本共産党の小池晃書記局長は13日の参院予算委員会で、大企業が株価つり上げのために「黒字リストラ」や自社株買いを進めていることを指摘。大企業のもうけを最優先した経済政策を切り替え、労働者を守るために政治が責任を果たすよう求めました。
■黒字リストラ放置
人件費を下げれば、コストカットにつながり、投資家の評価が上がります。このため株価つり上げを狙って、経営が黒字でも人員削減をおこなう「黒字リストラ」が広がっています。
東京商工リサーチによれば今年、早期・希望退職募集をした企業の約68%が直近の最終損益が黒字で、うち約8割が株価の評価が高い東証プライム上場企業でした。
小池氏は、「黒字リストラ」で企業の短期利益をあげて大株主を大もうけさせても、国民の暮らしは疲弊すると追及。「雇用に対する責任を果たすよう(政府として)いうべきだ」と迫りました。ところが、高市早苗首相は「労働者の自由な意思決定を妨げるようなことがあれば、適切ではない」というだけでリストラは野放しのままです。
一方、株主優先の経営は、本来賃金に回すべき利益まで株価つり上げのための自社株買いにあてています。そのため、大企業は空前の利益を上げながら、労働者の賃金は一向にあがりません。
小池氏が、政府の賃上げの具体策をただすと、城内実賃上げ環境整備担当相は「いろいろある。さまざまなやり方があると思う」とシドロモドロでまったく答えられず、高市首相は「経営資源を適切に配分するよう促す」というだけでした。
■労働時間短縮こそ
さらに、高市首相は、働きたい人がもっと働けるようにするなどとして、労働時間規制の緩和検討を指示しています。しかし、月80時間の残業規制を超えて働きたいという労働者は0・1%しかいません。小池氏は「労働時間の規制緩和は労働者の要求ではなく、財界側の要求だ」と指摘しました。高市首相は「本人の選択が前提」と答弁。残業代が減るために副業をし、かえって健康を損なう労働者がいるのを懸念するかのようにのべました。
しかし、労働時間を規制するのは労使に厳然たる力の差があるからです。「労働者本人の選択」などとしたら、際限ない長時間労働になる危険があります。高市首相が本当に労働者の健康を懸念するなら、残業せずにすむ賃金を保障することこそ必要です。労働時間の短縮を目指すべきで、規制緩和など論外です。
日本経済が「失われた30年」と呼ばれる長年の低迷から抜け出せない原因は、大企業が空前の利益をあげながら、株主配当を優先して賃上げに回さないため、富の偏在が生まれていることにあります。
大企業には、賃上げできる十分な体力があります。大幅な賃上げと労働者の権利を守るために、政治が責任を果たす必要があります。
【毎日新聞】11月16日<社説>財政健全化目標の後退 無責任な歳出拡大危ぶむ
予算が野放図に膨張し、借金頼みが更に深刻化しかねない。政権が掲げる「責任ある積極財政」とは程遠い姿になるのではないか。
高市早苗首相が財政健全化の目標を見直すと表明した。「基礎的財政収支(プライマリーバランス)」と呼ばれ、社会保障や公共事業など毎年度の経費を借金に頼らずに賄えるかを示す指標だ。
これまで赤字が続き、政府は「2025年度の黒字化を目指す」などの目標を掲げてきた。だが首相は「単年度のプライマリーバランス(の黒字化)という考え方は取り下げる」と大きく後退させた。
歳出拡大に意欲を示す首相は国債増発も辞さない構えだ。目標は妨げになると考えたのだろう。
だが国と地方の借金は計1300兆円を超えている。危機感が欠如していると言わざるをえない。
そもそも黒字化は立て直しの一歩に過ぎない。達成を先送りしてきた歴代の政権も目標自体は維持した。首相は「数年単位で確認する」とは述べたが、うやむやになる恐れがある。棚上げすれば、放漫財政に拍車がかかる。
首相は目標を「主要7カ国(G7)でも特異」と問題があるかのように主張したが、日本の財政は先進国で最悪だ。毎年度の収支すら黒字にできない方が問題だ。
代わりに首相が重視するのは、国内総生産(GDP)に対する借金残高の比率を下げることという。政府が先端産業に大規模に投資すれば、経済が拡大し、税収が増えて財政も改善すると唱える。
しかし成長頼みは危うい。投資先の半導体などは国際競争が激しい。成果が出なければ、借金が膨らむだけだ。首相が手本とするアベノミクスでも財政は悪化した。
最近の物価高で企業の売り上げが増えて法人税収が伸びるなど、税収全体は増加傾向にある。ただ、政府の歳出も増大し、借金を減らす効果は限られるといわれる。
懸念されるのは、財政不安から長期金利が上昇していることだ。財務省は想定より1%上がった場合、国債の利払い費は9年後に3倍の34兆円強になると試算する。
将来へのツケが一段と大きくなれば、社会保障費の急増が見込まれる超高齢社会を乗り切れない。持続可能な財政の構築へ明確な道筋を示すことが政治の責任だ。
【朝日新聞】11月16日(社説)経済財政の会議 偏った追認を危ぶむ
高市政権が力を入れる、経済政策を議論する二つの会議が議論を始めた。法律で規定された経済財政諮問会議と、経済政策の司令塔である新設の日本成長戦略会議で、ともに首相が議長を務める。
両会議で有識者として選ばれた計4人のマクロ経済学者とエコノミストは、いずれも積極財政派だった。首相の考え方に近く、バランスを欠いている。「責任ある積極財政」や政策実現の後押しへの期待が、透けるようだ。
単なる追認機関にならぬよう求めたい。将来世代の視点も忘れず、受益と負担の公平な関係や、財政への中長期的な影響にも向き合う姿勢が欠かせない。
諮問会議には、第2次安倍政権下で日本銀行副総裁を務めた若田部昌澄氏(早稲田大学教授)と、第一生命経済研究所の永浜利広氏が入った。城内実・経済財政相によると、首相と相談のうえ「高市政権にふさわしい方」を選んだという。成長戦略会議は、元日銀審議委員の片岡剛士氏と、クレディ・アグリコル証券の会田卓司氏が選ばれた。
それぞれの初会合では早速、この4人が政権の方針を後押しするような主張を展開した。政府が長く目標とする財政健全化の「基礎的財政収支の黒字化」について、「歴史的使命を終えた」などと訴えた。補正予算の具体的な項目となる経済対策では、前年の規模を上回らなければ、積極財政への「期待が低下する可能性がある」などと主張。積極財政論が目立つ会合となった。自民党内でも、規模の大きさを重視すべきだという声は強まっている。
思い出されるのは、第2次安倍政権下の日銀だ。
このとき政権は、金融政策を議論する審議委員に、金融緩和に積極的な「リフレ派」を次々に任命した。緩和導入時から副作用への懸念は指摘されていたが、日銀内でそうした声は小さくなり、緩和は複雑化し、長期化した。「デフレではない状況」になったが、大量に買い込んだ国債の残高圧縮など、緩和の「負の遺産」への対応は、今に至る日銀の大きな課題の一つになっている。
教訓を学ぶべきだ。経済政策の策定では、負の側面にも目を配る必要がある。「責任ある積極財政」は、物価高を長引かせたり、財政を悪化させたりする懸念がある。
首相は、初会合で「不安を希望に変える取り組み」を重視するとし、危機管理投資などを通じて「強い経済」の実現を訴えた。会議の議論が偏ることで、かえって不安をふくらませてはならない。